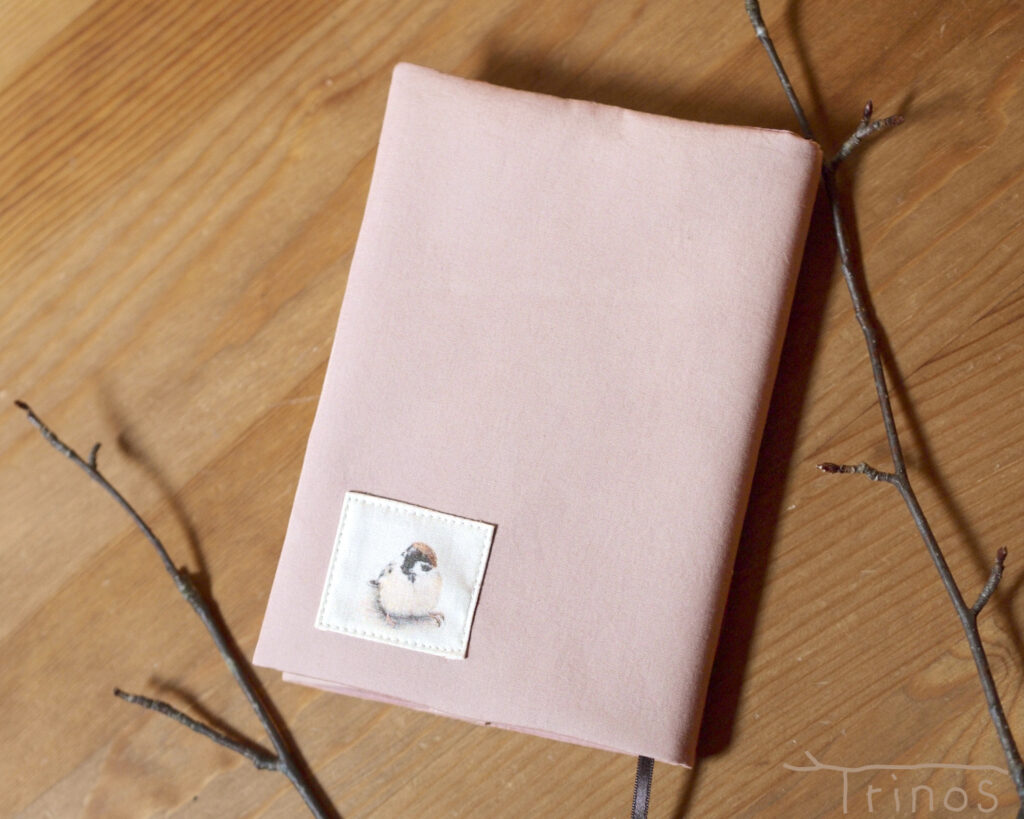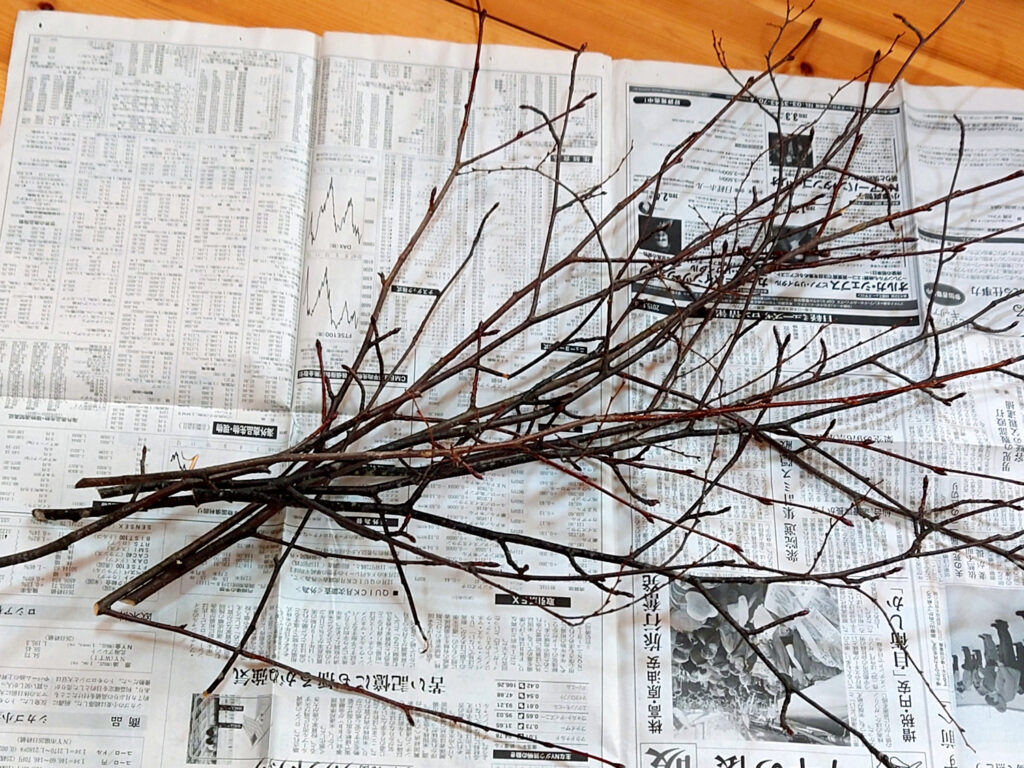ブログには書かないつもりでした。
けれどあまりにも多くの矛盾と問題をはらんでいて、
書きとめておくべきだと思い書くことにしました。
数年前の大規模な伐採によって切る場所なんてもう殆どなくなった近所で、
今週、百本くらいの木が切られることになりました。
道路に隣接しているアカマツとカラマツの林。
倒れたら怖いという地域の住人の声に、地主さんがやむなく切ることにしたそうです。
伐採を知らされたのは1週間前でした。

道路に沿って並んでいる40メートル程度分の木を切るという主旨ですが実際は道路際だけ切るのではなく、
道路から10メートル以上奥の方まで帯状に伐採。
40メートル x 10メートルの面積に生えている100本以上の木が無くなります。
業者さんは『手前を切ると風が変わって、奥も危険になるから切る』と言っていましたが、
作業の様子を見ていると、効率的に作業するためには重機で乗り入れる道が必要だから
奥まで切るのだと思いました。

重機で乗り入れたら、土壌は踏みしめられて団粒構造がなくなってしまいます。
そして奥に残されたわずかなアカマツ、カラマツはかなり細く風に強くあおられているものもありますが
そちらは切らずに残すという判断にも疑問を感じました。
結局木への配慮、土地への配慮はないのだと知りました。
『森の365日』(宮崎学著)の中で、長野県伊那の方でゴルフ場開発が決まった時に地元の方が
『未来の1万円より明日の千円を取ったのだ』と言っていたそうですが、
この地域で起きていることはまさにそうなのだと思います。
ずっと前からこの状態だった雑木林の隣に喜んで越してきて、
ちょっと枝が落ちて来たりするのを見て急に『木は恐い』と思い始め
今日、明日自分の家の屋根に木が倒れてくるかもしれないとおびえて切らせてしまう。
自分なりに木のことを学んだり、手入れを手伝ったりということはせずに。
森林面積が減る、土砂崩れの危険性が高まる、生態系への影響や地球温暖化、
という長い目で見た時のリスクよりも、
今日明日の自分の不安だけを取り去りたいと。
日本が抱えている問題が、顕著に表れているのだと思います。